|
1.はじめに:今私たちにとって何が問題なのか
今日、地球温暖化による気候変動が原因とされる、水不足・砂漠化・洪水・山火事の増大をはじめとして、都市集中、慢性的格差がもたらす治安の悪化、地域共同体の崩壊、食糧不足、エネルギー争奪など、私たちは多かれ少なかれ、自分たちの生活が不安に脅かされ、荒廃に向かっているのではないかと感じている。
しかしついこの間まで私たちは、急速な経済の発展と社会の進歩によって、大方の人々が豊かで便利な生活を享受してきたと考えて来たと思う。もの造りやビジネスの世界では、日々の経験や修練の積み重ねによって新しい発明や発見が生み出され、またスポーツや芸術の世界でも、日々の鍛錬と工夫によって次々に新しい記録がつくられ、新しい感性の世界が開かれて来た。一方政治や経済の分野でも、時代や社会の進展と共に、新しい政策やモデルが試みられ、問題解決にあたって来たはずである。それなのに、何が悪くて、あるいは何が足りなくて、今日のような事態に立ち至ったのであろうか。
私たちが考えなければならないことは、そもそも人類の進歩とは、あるいは文化文明の発展の歴史とは一体何であったのかという、人間の人間自身に対する根源的な問いかけを今一度自分自身に突きつけることなのではないかと思う。なぜならば、現代社会における本質的矛盾は、かつてマルクスが指摘した「労働と資本」の間のみならず、「政治権力と市民」の間、「強大国家・民族と弱小国家・民族」の間、「超繁栄と飢餓・貧困」の間、「異なる文化文明」の間、さらに「文明と自然」との間へと、止まることなく拡大再生産されているからである。しかもこれらの矛盾は互いに輻輳し合って現代特有とも言える危機的事態を拡大している。このような事態は、欧米近代化によって加速し、顕在化した側面をもってはいるが、もはやそのような狭い歴史的過程の分析だけでは解明できない性質をも持っている。
私たちはともすると、現代社会が抱える問題や矛盾を取り上げる場合、新しい技術開発や政策によって解決しようとする。例えば先進国がODAや投資の投与と併せて、後発途上国に自分たちが成功したと称する技術や開発モデル押し付けることが少なくない。また優れた学者や科学者、それにNGOやNPO などが、結果としてグローバル資本を下支えする例も少なくない。しかし科学・技術の進歩や、政策の転換というレベルの議論とは別に、今大事なことは、人類社会にとって歴史的視点に立ったグランド・ストーリーの復権と再生の議論、つまり欧米文化文明史の射程を超えたヴィジョンの構想が求められている。またそのときに忘れてならないのは、「人間存在とは何か」、あるいは「生きる意味は何か」という、人間の原点に帰っての明確な人間の自己認識と、その実存を克服する倫理・哲学である。
以下順を追って、現代社会の輻輳する問題の特徴とその拠って来る原因・背景を概観しつつ、求められている世界観・人間観の一端を垣間見てみたいと思う。
2.近代資本主義の現実とその行方
近代経済学の元祖アダム・スミスの『国富論』(1776年)は、これまでの貿易中心の経済から、産業革命後の産業中心の経済へ変化・発展して行く道筋を示した画期的な経済理論で、有名な「見えざる手」によって生産の供給と市場の需要が自ら調整し合い、新たな資本主義的発展を作り出すことを示した。一方同じ古典派経済学者であったマルクスは『資本論』において生産における資本と労働の関係に着目し、その間の矛盾が市場において新たな搾取と失業と不況を生みだし、資本主義の発展を阻害する事実を指摘した。その矛盾は一時は植民地への進出によって先延ばしされたが、二度の世界戦争という過酷な試練を経る一方で、幾度と無く社会変革の必要に迫られることになった。例えば社会主義革命とケインズ理論(『一般理論』1936年)による修正資本主義がその代表的な例である。しかし計画経済を主軸とする社会主義経済も、雇用と福祉を政策として採用する修正資本主義も紆余曲折を辿り、世界経済の主流から後退しつつある。またW.W.ロストウの『経済成長の諸段階』(1961年)に端を発する国連主導の途上国経済の発展政策も挫折の憂き目を見、早くからイノベーションによる価値創出による経済発展を唱えたシュンペーターの資本主義から社会主義への発展の道筋も見通しにくくなっている。その間に1980年代以降急速にネオリベラリズム派の政治経済理論が台頭し(いわゆるシカゴ学派経済理論とレーガン・サッチャー政治)、市場原理主義とも言うべき新たな資本主義経済が世界経済を跳梁しようとしている。
こうして今日、英米諸国をはじめとする政治権力は、「小さな政府」という一見合理的に聞こえる政策を唱え、その結果「ワーキング・プアー」の急増を招く一方で、巨大な私的資本の制限なき金融支配を許す事態を招いた。M&Aを梃子とする超国家企業による世界経済の寡占化が進むと同時に、いわゆる「はげたか」と呼ばれる投資ファンドがグローバル資本主義の下で、今や世界を股にかけて各種企業を買収することで莫大な利益を手にしている。投資ファンドは、銀行でも企業でもないため、その名前もほとんど知られていないが、この数年で国も政府もほとんど手の出しようがないところまで巨大化し、170兆円とも言われる巨大マネーを動かし、世界の為替市場や株式市場や商品市場までを左右する状況となっている。しかもこの種のファンドの動きは、私的投資ファンドに限られない。ロシアや中東では政府系投資ファンドがその運用資金を急増させたのをはじめ、今年になって社会主義国中国でも20兆円規模の国営投資ファンドが設立された。サブプライム問題で大きな損失を計上したシティグループやスイスのUBSに救済の投資を行ったこれら新興国の政府系投資ファンドのマネー総額は300兆円にも達すると言われている。
その一方で、世界の政治経済に大きな影響力をもつと自負しながら影が見えはじめた先進国、例えばアメリカやフランスの政権などが軍需産業や石油企業をバックに自分たちファミリーの私服を肥やすことに熱心であることは多くの人の知るところである。また日本をはじめとする少なくない国でも、政も官も財も癒着構造に胡坐をかき、国民・市民から徴集した金を裏金や無駄カネとして浪費し、公共的剰余価値の創出や社会問題解決のために心骨を賭す覚悟が見られないのが現状である。その間にも、これら巨大投資ファンドは企業の経営権を私物化し、世界経済を欲しい儘に支配しようとしている。かつてウエーバーが説いた資本主義の精神や倫理などは、彼らにとっては馬耳東風である。これらの事態は紛れもなく1970年代に動き出した「市場主義経済」と「ネオリベラリズム」がもたらしたものである。いったい誰が、何時、どのようにして、正に21世紀世界を跳梁し、人間と社会を荒廃させている、この怪物的グローバル資本主義を正し、矯正するのであろうか。
3.近代的政治制度の現実とその行方
広辞苑によると、民主主義とは「近世に至って、市民革命を起した欧米諸国に勃興、基本的人権・自由権・平等権あるいは多数決原理・法治主義などがその主たる属性であり、また、その実現が要請され ...人民が権力を所有し、権力を自ら行使する立場をいう」と定義されている。しかし市民革命以来今日にいたるまで試行錯誤を繰り返し、人民あるいは国民が権力を直接所有し、行使した例はパリコンミューンなど稀なケースを除けばなかった。多くの国では、人民あるいは国民が選挙で選んだ多数派議員が内閣を形成する制度を採用している。旧ソ連をはじめとする計画経済を柱とする一党独裁制を採る社会主義政権が頓挫したことは周知の事実であるが、なお一党独裁制下で人民民主主義体制をとる国も大国中国をはじめ数カ国存在する。しかし多数党制を採る国でも多数派政権が長期間続けば、政権内の腐敗・汚職などが横行し、国民の自由や平等が置き去りにされることもまた少なくない。いずれにしろ欧米近代史は進んでいるとも後戻りをしているとも見え、今日に至るまで試行錯誤を繰り返して来たと言える。そのなかで近年注目すべき変化がある。
ひとつは、上の2でも述べた、レッセフェール政策への回帰とも言える「ファンド資本主義」という巨大な投資ファンドの登場である。アメリカをはじめとする、世界の大手銀行・証券もこれに資金を提供し、企業の吸収合併だけでなく、企業そのものの売買ゲームによる前近代的とも言えるルールなき市場の独占化と金融支配が国際社会を跳梁している。しかも先進国のいかなる政府もその実態解明に無関心であるばかりか、その活動をコントロールする気配も見られない。「小さな政府」の名による規制緩和がいったい誰のためのものなのかは欧米に限らず、残念ながら最近話題になった2兆円と言われる防衛装備予算に群がる日本の例も含め、何処を見回しても利権の闇は広がる一方である。
次にいまひとつ最近注目されているのが、資源ナショナリズムである。資源大国と言われる中国、ロシア、オーストラリア、南米、南アフリカなどの国が、欧米大国が中東に目を奪われているなかで、資源ナショナリズムを唱え、積極的な資源外交を進め、関係を深めている。東アジア共同体戦略でも遅れをとった日本は、食糧や石油をはじめ、日本が売りものにしてきたハイテク産業に不可欠なレアーメタルなどの資源確保にも遅れをとっているのが実態である。そうした中で、民意を委託された外国の政府あるいは政治権力が国の内外でどのような役割を果たしているのあろうか。例えばアメリカがこの十年余にわたってアフガニスタンやイラクに対して、国際正義やテロとの戦争を旗印に軍事力を行使して来たが、その結果はアジアと中東に平和と安定ではなくむしろ混迷を、自国の権益にも戦費の浪費と財政赤字をはじめ、石油資源の確保さえままならない状況をもたらした。いったいアメリカ国民の誰が救われ、誰に福祉がもたらされたのであろうか。アメリカの友好国といわれる国では、一時の自由主義政権への流れがフランスを除けば、次々に左翼政権や中道左派政権へと変わって来ている。またソ連崩壊後停滞を続けてきたロシアでは、資源外交を軸にアメリカに対抗する国力を身につけ始め、中国は幅広い経済外交を積極的に進め、資源の確保においても世界の工場としても揺るぎない地位を築いており、バブルや公害や格差問題についても先進資本主義国の轍を踏まない政策の検討に入っている。政・官・財の間に癒着を生みかねない構造は、資本主義国であるか社会主義国であるかにはあまり関係なく起こる問題であると思う。もはや軍事力を背景に自国の権益を主張する国際関係の時代は終わらなければならいという国際的コンセンサスが出来つつあると考えるべきであろう。ネオリベラリズムが何をもたらしたか、また自由民主主義政権が唱える「小さな政府」が偽装か幻想に過ぎなかったこと、また一党独裁の下での「社会主義」体制にももはや限界があること、いずれにしろ政官財癒着の構造を断ち切ることと、国民(人民)に現実の問題を詳らかにした上で、地球時代に求められる自然との共生の上に立った人間の安心・安全と、国際関係を率直に認める必要があると思う。
軍事力やカネの力に頼らない、資源と技術と人間力を分かち合う社会の実現には、いかなる制度の構築が望まれるかを、それこそ国境と超え、民族や伝統文化や価値観を超えて、周知を集める作業からはじめることが今何にもまして大事なことである。そして日本の現状について言えば、既得権益の下で、将来への夢も保証もないまま、多くの国民が泣かされている今の現実は、誰によってもらされたものなのか、そして何よりいかなる制度疲労によって起こされたものなのか。その拠って来る遠因を尋ね、突き止め、その抜本的解決のヴィジョン、グランド・シナリオを真剣に構想する必要があると思う。
4.近代的社会環境と文化的価値観の現実とその帰趨するところ
冷戦崩壊後、民族ナショナリズムや伝統的宗教への回帰とも言える動きが目立ち、それも一時沈静化したように見えたが、その後「国際正義」や「テロとの闘い」に名を借りたアメリカによる世界への覇権追求の動きが強まるに従い、それに対抗する形で民族ナショナリズムが、ロシア、中国、南米諸国などに台頭している。覇権や独占や一人勝ちを目指すことが許されている限り、国でも、地域でも、組織でも、個人でも、利害を共有する者の間での同盟と連帯は、生き残りのための有力な武器となる。しかしそれは国であれば大国、企業・組織であれば大企業・組織、個人であれば社会の上層階級に位置する者の間でできることではないだろうか。だがそういう国であれ、企業・組織であれ、地域であれ、個人であれ、何時、没落、倒産、ドロップアウトの憂き目が自分を待っているか分からないのが現実である。
六年余前に刊行された『地球村の思想』(新評論、二〇〇一年十二月)の「序論」の最後のところで、私は、現代社会が直面している現実とそこに至った背景・過程を指摘した上で、「三つの軛からの脱却」、すなわち「国家・政府・行政」と「企業・団体」と「文化的アイデンティティ」からの解放の必要性を強調した。当時ある評者たちは、「あれはアナーキズムです」、あるいは「あなたは政府や行政が嫌いなのですね」と私のことを皮肉った。しかし政府や行政、企業や団体に対して、その理不尽と無責任性や、モラルハザードと非社会性を、市民・消費者として、監視し、批判し、これと闘うことと、自分自身をそこから解放し、自らを頼む強い意志をもつこととは別のことではないだろうか。例えば政治や法律や団体に多くを期待することが出来ないとき、また伝統や地域や文化的アイデンティティに心の拠り所を求めることに限界を覚えるとき、己を頼む覚悟を、つまり現実が私たちの期待を裏切り、過酷な状況を突きつけて来るとき、私たちたちとしては己を頼む覚悟が出来ていなければならないと思う。
人は、もの心がつき始めるころから、大人の世界の理不尽に気づき始める。社会に出ると、なぜこのようなことが許されるのかと正義心を揺り動かされ、反発もし、抗議することもあるが、多くの場合正義は裏切られる。そのうちに生活と仕事に追われようになり、あるときは善意の他者の求めに応じ、あるときは悪意の他者と闘いながら、やがてそういう社会や世間と間合いを保ちつつ、己を頼む日々を生きることができるようになる。それでも、自分とは何か、人は何のために生きているのか、あるいはこれで良いのかという意識は、通奏低音のように、人の心にまとわり続ける。
近頃日本の政治家は競って「安全安心」を口にし、世間もそれに対して負けずに、「セイフティ・ネットを」と主張する。しかしそれは、社会がいかに危うい状況におかれているかの裏返しであり、正に現実が、このような状況を一朝一夕で改善することができないことを如実に示している。政府も官僚も企業も団体も、自ら責任を取ることは極めて稀である。このような不条理な社会や世間に在って、多くの人は、時にあるいは一度ならず、挫折を経験し、孤立無援のなかで耐え、闘い続けなければならない。確かにそういうとき、己の信じる神仏への帰依が心の支えになり、歌心や伝統的価値観が心の拠り所になることもあるし、ひと時の癒しともなるであろう。「足るを知る」という古くからの教訓があるが、このことばが意味している真理は、人の身体も精神もこれで足るということがないということである。つまり人は誰しも、命尽きるまで、世間を受け入れつつ、また他人と間合いを保ちつつも、結局己を頼まなければ生きていくことが出来ないのである。
アメリカの爆撃で多くの子供たちを失ったイラクの親たちの嘆きと恨み、異常気象による竜巻と洪水で家も肉親も無くしたニューオリンズやバングラデシュ南部の人々のやり切れない思い、豊かな国日本と言われるのに、終わることのない薬害に苛まれる人々の苦痛。そこには、歴史も文化もおかれた条件も違うけれども、なぜ私たちはこのような酷い、理不尽な災難に会わなければならないのかというやり場の無い悲痛な思いと怒りがある。確かにこういう私たちの生きる世界は、ある詩人が記したように、「叶えられない望み、苦悩の沼地、世界の破滅」そのものではあるが、そうであるが故にまた私たちは、「あばら骨をむきだしにして」、「らんらんと輝く真っ赤な竈に心臓を差し出して」、この世界と闘いつづけることが出来るのである(丹羽京子訳『バングラデシュ詩選集』、07年11月、大同文化基金)。
文明の歴史が勃興と没落と再生を繰り返してきたように、いつの時代においても、社会や世間にとっては変革と革命が、またそういう社会と世間とたたかいつつ生きる己には自己革新が永遠に求められる。それが人間であることの運命であり、また生きていくことの意味である。
5.終わりに:「蒼い地球村」再生のための課題と具体策の検討
以上概観してきたように、どの国に対しても、いかなる個人に対しても、同じレベルの自由と平等を保証できるような国際システムをつくり、社会環境を整備することは、欧米近代文明が歴史的に積み上げてきた枠組みのなかでは困難だと言える。十九世紀の中頃パリに滞在したドストエフスキーが、その『日記』のなかで述べたように、最初に不平等がある所で「万民に平等を」と唱えても実現することはもともと叶わないことだったのかも知れない。近代における科学の進歩や産業革命の実現によって、その恩恵を受けたのは一部の先進国であり、一部の富裕層であった。その間にも戦争や略奪や搾取は止むことなく続いてきた。そして何より今日、資本主義が支えて来た三度の産業革命を経て人間社会が手にしたものは、いささかの「生活の便利」と溢れる「モノ」と移動の「速さ」などの類である。それで人々が幸せになったと言えるであろうか。「人民による人民のための人民の政治」についても同様である。しかしその限界を突き破る政治の在り方や経済社会システムを実現することを諦めることはできない。なぜならそのための努力を放棄することは、1万年とも10万年とも言われる文明の歴史を担ってきた人間の存在理由そのものを否定し、私たち一人ひとりが人間であることを止めることを宣言することに他ならないからである。
最後に、これまでの議論を前提として、以下若干の問題提起をしたい。
第一に大事なことは、私たちが「人類再生シリーズ」を通して述べてきたことであるが、人生観であれ、世界観であれ、歴史観であれ、「進歩」・「発展」・「成長」を金科玉条のごとく信奉してきた価値観を根本から問い直すことである。欧米近代化の基本には、人間が地球の主人公であり、人間が神に成り代わって自然を支配し、コントロール出来るという世界観の確立があった。三度の産業革命も「神の見えない手」と偽って市場を我が物顔に支配し続ける自由な資本も、自由競争原理の下で勝ち組・負け組み競争を煽り立てる適者生存=弱肉強食を先ず根本から取り除く必要がある。そのためには、今日世界経済を支配している、私的セクターであれ、政府系であれ、投資ファンドという名前のグローバル金融の無秩序な暗躍を正さなければならないであろう。
第二には、都市化と市場経済化してきたこれまでの経済社会システムを、集中から分散へ、画一化から多様化へ、グローバル化から地域化へ、バランスと調和あるシステムに大きく転換することである。例えば最近日本も関わる東アジア地域で試されている共同体構想についても、EUと比較して困難な課題を抱えていると言われているだけに、その実現に向けた問題解決のシナリオが一つの試金石になると思われる。
第三には、欧米先進国主導の開発と援助政策が進められる過程で、様々な矛盾や問題が浮上してきた以上、水、資源、食料、環境、治安などすべての課題の解決について、先進国主導での国際間・地域間の従来のやり方を根本から改める必要がある。そのための新しい地球村秩序にむけたこれまでとは異なる考え方や原則を定める必要がある。
第四には、自然環境と地域共同体を重視する経済への大きな転換である。最近メディアをはじめ、一部研究機関や企業などで、アメリカのワールドウオッチ研究所の創設者レスター・ブラウンの、「環境コストと社会的コストを市場価格に織り込んだ」新修正資本主義が高い評価を得ている。しかし大事なのは、ブラウン流の市場経済なのではなく、彼が1984年に創刊した『地球白書』の冒頭で、「私たちが直面している事態は、私たち自身がつくり出したことであり、私たちにコントロールできるはずである。これ以上の技術的進歩がなくとも、全ての問題は解決できるし、すべての人間の基本的要求は満たされうる。つまり問題は技術や資源ではなく、認識と政治的意思である。」と述べた彼の原点である。日本について言えば、農林魚業の後退もしくは食料・飼料の自給自足体制の荒廃をいかに再生することができるか、インフラ整備を修正し、製造業とサービス業(流通を含む)と農林魚業とのバランスを自然環境と地域共同体を重視する視点から練り直し、大きく転換する必要があろう。
第五には、これまで私たち人間が自己の利益のために自然を支配し、利用し続けてきた科学技術の開発に思い切った歯止めをかけることである。そのことによって、今もっとも私たちに求められている他生物との共存や、地球環境との共生が可能になるからである。そのためのラディカルな選択が、私たち一人ひとりに突きつけられていることをしっかりと認識しなければ、多くの人たちがこれまで描いて来た控えめな「地球村」の将来像も、世界を跳梁しようとしている貪欲な文明人の手にかかって踏み砕かれてしまうであろう。またこの問題は、科学技術の開発とも連動している。世界の大国を自称する国々における軍事力の拡大と核兵器を含めた開発は、世界中の民の労働と生活に対する不断の脅威となっている。「暴力には暴力を」の連鎖を断ち切るためにも、武器を手段とした国家の暴力を厳禁しなければ地球市民の平和は決して実現できないであろう。そのためには武器の生産と使用を今後一切禁止することが必要不可欠である。文明の進歩は、「人間一人を殺戮する技術の価値と費用の高騰にある」という意見もあるが、国家間、諸民族間、市民間での対立・矛盾・抗争が絶えない今日、欧米流の世界秩序ではない、地球人万人のための安全と安心が可能となる「地球文明」の在り方を根本的に構想することが求められている。
最後に、以上のような認識の上に立ち、衰退しつつあると言われる文化発信力を再起動させ、国際的で地球的な合意形成のための行動提起を速やかに起案しなければならない。今回の私たちのGN21としての徹底した議論がその一里塚となればと思う。
|
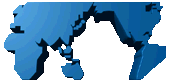 G
G
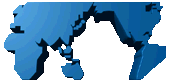 G
G